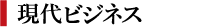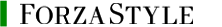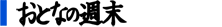※撮影時以外はマスクを着用の上、感染症対策を実施しております。
サッポロラガービール、通称“赤星”を求めて夜な夜なそぞろ歩く、赤星100軒マラソン。回を重ねて第73回を数えます。今回目指したのは池袋です。大都会であり、古い店、新しい店、たくさんある街なのですが、実はワタクシ、あまり馴染みがない。
東京は都内と言われる23区のあるエリアより、西に広がる市部、郡部のほうがはるかに広い。私は三鷹市に生を受けて以来一度も23区内に住んだことはなく、広大な多摩エリア内で2度、3度と引っ越しをして現在に至るので、東京都心は我が町というより、出かけていく先であるという関係が未だに続いている。

三鷹市の中でも私が育ったところはJR中央線と私鉄の京王線の中間より少しばかり京王線に近いあたり。つまり都心への玄関口は、いずれの路線を使っても、新宿ということになります。新宿という巨大な副都心には何でもあるから、自然と他の街に行かなくなる。というより、行く必要が見つからない。したがって、新宿同様の副都心である渋谷にも池袋にも不案内ということになったのです。
久しぶりで池袋の街へ出た私は、ちょっとクラクラする。神田や浅草といった昔ながらの家屋が残る街に酒場を訪ねるときは、のんびりと散歩するくらいの気軽さで出かけられるのに、あまりよく知らない巨大都市に身を置くと、周囲の人々がどこへ向かって先を急ぐのか、果たして自分は今どこを目指しているのか判然としなくなるのだ。
私はクラクラしながら、自分の勘がアテにならないことをあっさり認め、スマホのナビを頼りに目標の店「うな達」を目指した。

■地下空間に広がる老舗の風格
ありました。無事にたどり着いた。いやしかし、この店、実にシブいぞ。
道に出している看板には、「うなぎ・鯉・どじょう、魚・季節一品料理」とあって、その横に小さく、「うなぎ串焼、ひれ焼、きも焼、一口蒲焼」とあって、さらに、「出前仕出し承ります、蒲焼・うな重・うなぎ弁当、仕出し弁当」とあって、ここがいかなる店であるかひと目でわかる。

さらにシブいのは入口だ。3巾に割れた暖簾を潜るとそこは右手に手すりのついたやや急な階段で、下りて右へ入ると、左手に調理場、正面から左手の奥に、コの字のカウンター席が見えている。
ふと右手を見て驚く。そこは広めの座敷で、座卓がいくつも並べられている。階段を下りている最中には、地下にこれほどの空間が広がっているとは想像もつかなかった。そして、店内には、老舗の風格がある。

カウンターに席をもらって赤星を頼み、大将に伺うと、創業は昭和49年ということです。ということは今年で48年目。私は飲兵衛生活40年の、なかなかのベテランであると自負しておりますが、そんな私が11歳の頃にはすでにこの店はスタートを切っていたのです。お見それいたしました。
さっそく、串焼きのセットを注文します。

「うちへ来るお客さんは、必ず食べるよ。でも、セットの場合も、単品でも、串焼きはおひとり様1本までと決めてるの」
串焼きのセットは、さきほど看板で見たとおりのもの。ひと口蒲焼、ひれ、きも、かぶと、の4本。

かぶとは鰻の頭のことだから、当然ながら、鰻一匹から一つしか取れない。ひれは背びれとのことで、これも、1本の串焼きに、鰻二匹分の背びれが要るとか。きもも同様。何を言いたいかというと、いずれも希少部位であり、それゆえに、おひとり様1本までということなのだということだ。
さて、さっそく食べてみる。まずはお馴染みのきもから。赤星をグラスに注ぎ、ぐいっとひと口飲んでから、きもをひとつ。

ほろ苦さの競演。最初の一杯に合わせる最初の酒肴として絶妙の調和がある。
さてさて、お次はひれだ。背びれとニラを巧みに巻き付けたもので、私は初めて食べる。
これがまた、うまい。魚類の皮の独特の脂とはまた別の旨さがあって、目を開かれる思い。ひれまで喰っちまってごめんよと、可愛い鰻に挨拶したいくらいのものなのだが、口中でほろりとほどけるかぶとがまた、ニクイ。

魚は頬や脳天、鼻づらにカマと、顔から首にかけてがうまいとされるけれど、鰻も同様で、口に慣れた蒲焼とはまた違う食感と味わいが、ビールにとてもよく合う。
■酒を飲む人、ご飯を食べる人
串焼きは店の名物。来る人はみんな頼むというくらいの人気の品。それゆえに、諸物価高騰の昨今はおろか、それ以前を含めてずっと値段を変えていないという。
ちなみにそのお値段ですが、かぶと焼100円、ひれ焼120円、きも焼140円、一口蒲焼200円。安いね、たしかに。

“ちなみに”を重ねて言えば、蒲焼、白焼のお値段も、竹1200円、特1700円、特上でも2200円と良心的。開店直後から三々五々やって来られたお客さんたちの注文を小耳に挟んでも、目的が酒で、鰻はひとまず串焼きでいこうという人と、最初から食事がメインという人の両方が混在しているようだ。
もろきゅう、たこぶつ、山芋千切り、にら玉、サンマ焼、サバ味噌煮、煮込みにどじょう煮、おにぎり、ざるそば、それから焼肉丼などというしっかり食べるメシ献立も用意している。

実はこちらのお店、日替わり定食などを出すランチ営業もしているそうで、金曜日のお昼には長い列ができる。その日は何が出るかというと、カレーライス。昔ながらの昭和のカレーライス。もとは賄いのメニューだったものをランチに出したところ、たちまち大変な評判となったそうです。
それはさておき、編集Hさん、写真のSさんと座敷で合流した私は、赤星隊の一員となってリラックスタイムに入ります。卓上には鰻の骨を揚げて塩をパラりとふった、この店で言う、「カルシウム」が並んでいる。

さあ、赤星を追加して、次なるつまみも追加しようとあれこれ頼んだテーブルには、まず、もつ煮込み豆腐とサンマの塩焼きが出た。いずれもビールのつまみには最高だ。

味噌のほどよい塩味を効かせたモツの煮汁と豆腐とのバランスが絶妙で、言葉はちょっと大袈裟になるけれど、一体感のある正統派煮込み豆腐と呼びたいひと皿なのである。

この季節のサンマの塩焼きもいい。角皿の上にスラリと横たわりけっして威張ることはないのに、箸で身を崩して醤油を垂らした大根おろしをのせて口へ運べば、おお! これぞサンマの塩焼き、たまんねえな、と言わしめる。

赤星を置くようになったのは、大将によれば「10年くらい前かな」。評判がよく、今ではビールを6ケース注文するなら4ケースは赤星だという。
調理場で大将と一緒に仕事をしているお兄さんによれば、
「ああ、赤星あるのか、って喜んでくださる方が多いんですよ」
とのことである。

わかるね。そう口にするお客さんの気持ちが、私にも。
■この安心感はどこから来るのか
お客さんは、次々にやってくる。厨房も、ホールも、ちょっとの暇もない時間帯に入ったようだ。若い人もいる。飲み会という感じの3人組もいる。開店直後からカウンターにいるカップルも、実に楽しそうに飲んでいる。
カウンターの下にびっしりと詰まっているのは焼酎の一升瓶で、お客様の多くはこの一升瓶をキープして、ロック、水割り、レモン炭酸割りなど、お好きな飲み方で楽しまれるようなのだ。

店がそこそこに混み始めてから入店した人がうな重を注文すると、女将さんがまず厨房の大将に通す。すると大将は、「40分くらいは時間をいただきます!」と、必ず丁寧に確認をする。私たちの滞在中にもそういうお客さんが何人かいたけれど、ああ、じゃあ、いいですと店を立つ人はいなかった。
うな重かあ。うめえんだろうな、と、そのやり取りを聞いていた私は思う。そして、今度来るときは、きっとうな重にも手を出そうと決心するのである。

お客さんの一人は、女将さんと中学の同窓だという。そして、お連れの男性のほうは、大将の高校の後輩であるという。何中学なのか、何高校なのかは聞かなかったけれど、同じ文京区であるとは聞いた。
文京区と言えば東京23区の中でもひときわ教養レベルの高そうな、文化度の高そうな、うーん、書いている自分でもよくわからない印象を持っているわけですが、なんだか、それはそれでローカルで温かい感じがする。只今、この瞬間でさえ、池袋のど真ん中にいるのに、どこか郊外の常連ばかりが集まっている気楽な雰囲気の店のような気もするのである。

「みなさん、全然、ピリピリしてない。柔らかいんですよ」
店内の撮影が一段落した写真のSさんが、ご主人はじめ、店を切り回す4人の方々の印象を口にした。
ああ、そうだったのか。この安心感というか、ホッとさせるような雰囲気は、店サイドのみなさんの和気あいあいが引き出してくれるものだったのか。今さらながらそれに気づいて店を見回すと、どのテーブルも、カウンターのどの席も、みなさん、リラックスして過ごしている。

いいなあ、いいもんだなあ……。
すっかりぼんやりしてしまった私の向かいで飲んでいる編集Hさんのところに、特製のTKGがやって来た。うなぎのタレを垂らしたご飯に生卵をかけるらしい。

ずるずるっとかき込んだHさんは言った。
「ああ、なるほど、そうか。すき焼きの余った卵をご飯にかけたみたいな味になるんだ」
それを聞いた私は即座に、追加をひとつ頼みたくなった。

(※2022年10月14日取材)
取材・文:大竹 聡
撮影:須貝智行








 ブックマーク一覧
ブックマーク一覧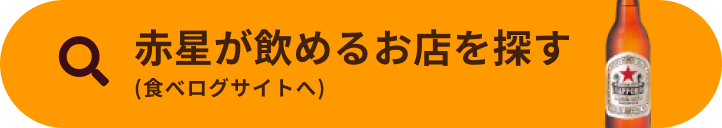






 と赤星
と赤星

 と赤星
と赤星