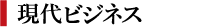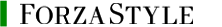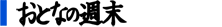※撮影時以外はマスクを着用の上、感染症対策を実施しております。
浅草、浅草寺の裏側、通称「観音裏」に、カウンター7席の小さな酒場がある。その名も「酒さかな ずぶ六」。
ずぶ六とは、とても酔っている状態のことを指す。江戸時代にはこのような言い方が始まっていたらしいのだが、「ずぶ」の後の「六」は、酔いの程度を示しているという。六は、とても酔っていて、もうかなり出来上がってしまっているが、周囲に迷惑がかかるほどではないようでもある。これが、七、八となると、それはそれでたいへんで……。このあたり、『居酒屋の誕生─江戸の呑みだおれ文化』(飯野亮一著・ちくま文庫)に詳しい。

とても酔ってはいるが狼藉を働くわけではない状態、これをずぶ六とするならば、飲み屋さんからしたら、そろそろ締めでよろしいのではないですか、と声をかけるタイミングであり、酔客からすれば、躓いて怪我をしないうちに家にたどり着こうという、潮時を意味するのか。考えてみれば、そのぎりぎりのあたりが、いちばん気持ちのいい酔い加減かもしれない。
もとより、ほろ酔いこそ一番と考える人もいるだろうから、ずぶ六が最高というのは酒飲み生活40年の筆者のあくまで個人的な見解です。
それはともかく、この渋い暖簾のかかった小さな酒場にじっくり腰を落ち着けることができるならば、その人にとってちょうどいい酔いの境地に導かれることは間違いないだろう。

■わずか7席の客をもてなすために
ビールはサッポロラガービール、“赤星”のみを用意する。
これまでいろいろな酒場で飲んできた経験から、これが好きだから自分の店にも置くことにした。そう語るのはご主人の谷口賢一さん。2017年に独立開業する以前は、飲食店に勤務し、ホールでのサービスから、調理場を経験してきたという。

お通しは、3品出た。
「ひたし豆と、バイ貝と、古代米の酒粕でつくった甘酒です」
お猪口の中の小豆の汁を思わせる甘酒を飲んでみて、思わず、声が出た。冷たく、そして、うまい。
「これはうまいですねえ。なんだろう。フルーツのような……」

「ベリー系のものが入っているの?と訊かれることもあります。この季節には、おいしいと思います」
聞けば「伊根満開」という京都・丹後の酒蔵が醸す古代米酒の酒粕を、蔵元から取り寄せたという。
「お湯に溶いて、砂糖と、塩も少し。それだけです」
この色は、紫小町という古代米そのものの色らしい。見せてもらった酒粕は、濃い小豆色をしていた。

ビールに口をつけ、ぐいっとやる。お通しのひたし豆をひと粒。そしてまた、ビールをぐいっとやる。茹でたての枝豆もいいが、この季節、さっぱりと冷たいひたし豆というのも、なんともうまい。出汁の加減がまたよくて、食欲をそそられる。
訪ねた日は、営業開始の少し前からお邪魔をさせていただいた。普段なら仕込みも終えて、一休みしている頃か。それが気になったのは、この店の壁にある品書きの豊富さに気づいたからだ。7席の客をもてなすために、これだけの品数を揃えるのは、並大抵のことじゃない。

刺身の魚は、カツオ、キンメ、コチ、イサキ、タカベ、白イカ、イワシ、サバ、ニシン、カマス、タコブツが並び、肴としては豆腐や煮魚、うな肝、アユうるかなど、いかにも酒に合いそうな品を用意。
さらには、塩サバの香草バター焼き、つぶ貝アスパラ酒盗炒め、ねぎとろ奈良漬け和えなど、ひと工夫ありの料理に加えて、地ハマグリやイカゲソ、クレソンや水ナスなどをタネにしたおでんもあり、抜かりなく品書きの隅々まで見渡せば、おでんの出汁茶漬けあり、ハマグリ茶漬けあり、イカ墨雑炊なんて、魅惑のご飯ものが視界に入る。

店では、調理場の端、外へ面した窓のところに長火鉢を置き、そこへ七輪を設えている。使い勝手は、必ずしもいいわけではないと、谷口さんは笑うが、あそこでナニか炙ってもらったら、それだけで楽しい気分になれそうだ。
そうするうちに、小さな陶製の釜で、飯が炊きあがった。谷口さんは湯気をたてる米をお櫃に移し替える。

「ご飯ものはあまり出ませんが、とりあえず1合焚いておけば、お茶漬け2、3杯分は間に合いますから」
酒肴の中から、煮穴子と、鶏ささみ昆布締め茗荷和え、それからお造りの盛り合わせを注文。煮たバイ貝の身を口に放り込み、歯ごたえと、じわりとにじみ出るうまみを存分に味わいながらビールををまたぐいっとやる。

■仕入れにも仕込みにも手間を惜しまない
お造りの皿が来た。キンメダイ、ニシン、イサキ、カツオ、白イカの5点。ニシンとイサキは皮目を軽く炙ってある。
「今日はサバがいまいちだったので、ニシンにしました。カツオだけは生のままです。これは辛子で召し上がってください。あとは、少し熟成させています。塩とスダチか、ワサビ、お好きなほうで召し上がってください」

見た目に美しいし、つまみながら酒をゆっくり味わうには、量もほどよい。なんともセンスがいいなあ、と思いながら、まずは、唯一の生であるところの、カツオに箸をのばす。
辛子を少しつけ、醤油も少しだけ。口へ運ぶと、この鮮度、この脂、そして春のカツオの爽やかさの名残りが存分に楽しめる。今年喰ったカツオの中で一番だと思う。嬉しいねえ。

ビールをそろそろ飲み干すタイミングで、この魚だ。ちょっと早いが日本酒をいただきたい。酒の品書きに目を走らせると、燗でも冷やでもOKの酒には、生酛、山廃、水酛などが多い。私は、今年の正月に大阪で覚えた「遊穂」という能登の酒を選んだ。
ニシンからイサキへ、皮目を軽く炙ったのをスダチと塩でいただく。ニシンは脂ののりがほどよくて、イサキにも旬の魚のうまみがつまっている。それから白イカ。つるりと滑り込んできてコリっとした軽快さを見せ、ワサビの風味と一緒にとろりとした甘みも残す。

ひとりで切り盛りする中で、燗酒の塩梅を見るのはたいへんだと思うが、遊穂の燗は完璧だった。山廃の純米、醸造は2017年だから、熟成もしている。それが、猪口の中の液体の色に現れている。
キンメの刺身がまた格別だ。ほどよく水分が抜け、うまみが増している。少し熟成させるからこそ、これだけの魚種を、日替わりで用意できるのだろう。仕入れにも仕込みにも相応の手間がかかっていると今さらながら気づく。

「埼玉県に住んでいますが、そこから浅草まで片道15キロ、毎日自転車で通っています」
途中、千住の市場で日々の仕入れをするという。仕込みは毎朝9時頃から。そして、深夜、自宅に着くのは午前1時を過ぎる。それから少し、酒を飲み、ぐっすり寝て早起きをし、3人の娘さんたちと顏を合わせるという。
まさに、全力投球の毎日だが、谷口さんの印象はあくまで穏やか、とてもクールである。

「どうやって作るのか、おつまみのことをお客さんに訊かれることもありますけど、僕は全部、教えちゃいます。レシピまで(笑)」
こりゃ人気が出るよねえ……。
と思うまでもなく、私たちの取材当日も、6時半からは予約で満席ということだった。

■どうにも調子が出てきてしまい
煮穴子は、熟成した生酛の燗酒にとてもよく合う。店は、少し濃い味わいの食べ物にも合う酒を揃えているのだろうから、銘柄がよくわからないときにはお任せしてしまう手もある。
鶏のササミの昆布締めに茗荷を和えた一品は、見事というしかないアイデアだ。味わいの豊かさと爽快さを兼ね備えている。

「料理はまったくのオリジナルではないです。日ごろ、見聞きする中で、これいいなと思うものを、そのままではなく、少しアレンジしてお出ししています」
さて、今度は冷や酒に、合わせたい。頼んだのは秋田の「飛良泉」純米大吟醸。これがまた、めっぽううまかった。
「いいねえ。いい酒だねえ」「ええ、うまいですよ」
会話はこれだけで十分。秋田県はにかほ市の酒とのことで、にかほといえば、象潟の岩カキ、なんてことも頭をかすめる。どうも、調子が出てきてしまったようである。

ではこのあたりで、棚にある、洒落た蕎麦猪口で和らぎの水をもらっておいて、さらなる酒に向かうか……。
いや、編集Hさんもそろそろ私の隣に座って飲み始めるタイミングである。ここは迷わず、この日2度目の「赤星!」といこうじゃないか。

(※2022年7月8日取材)
取材・文:大竹 聡
撮影:須貝智行








 ブックマーク一覧
ブックマーク一覧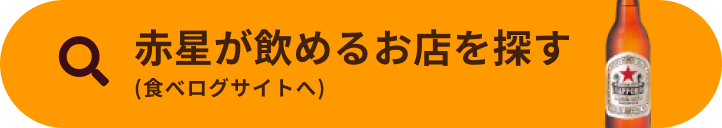





 と赤星
と赤星
 と赤星
と赤星

 と赤星
と赤星