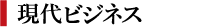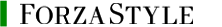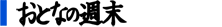多摩生まれの多摩育ちで下町にはとんと疎い。自他共に認める田舎者のわたくしですが、実は20年ほど、日本橋馬喰町に仕事場を持っていました。
当然、近所で飲むわけですから、下町知らずと言いながらも、馬喰町、人形町、東神田界隈の酒場はちょっとばかり知っている。仕事場があったのは、30歳から50歳までの20年で、私の人生が加速度を増しながら「酒一直線」になっていった時期と重なります。
とはいえ、30歳を超えたばかりのころは、カネがなかった。20代は営業マンとして過ごして、まあまあ人並みに暮らせていたのに、29歳になったとき、ああ、もうやめたやめた! と、なんだか妙にはっきりと思い決めてしまった。
それから1年弱は知り合いの事務所で編集の見習いをさせていただき、満30歳になった翌月に、言葉は大袈裟にすぎますが、「独立」をしてしまったわけです。

仕事場はフリーの寄り合い所帯だから、お互い、上司でも部下でも同僚でもない。それぞれの仕事をして、それぞれのタイミングで生きている。だから、「さあ、今夜も行こうぜ」と誰からともなく誘いの声をかけて飲みに出る、という具合にはならなかった。
なんだか、妙に淋しい。馬喰町から浅草橋駅へと歩きながら、馴染みの店の1軒もない浅草橋界隈で、大袈裟ですが途方に暮れるような夕べがありました。
そのとき、JR総武線のガード下からもくもくとわきあがる煙が私の目に飛び込んできた。この道を歩くたびに目にしてきた煙。もつ焼き屋の煙とわかっている。そのとき、ひらめいたんですよ。
ああ、そうか、あそこへ、ひとりで入りゃいいんだ……。あそこの仲間になっちまおう。

私は店の前の道路にまで立ち飲みの客があふれ出しているその店の、背広姿の男たちの背後に立った。
「ビール。それからタン塩2本!」
「はいよー!」
「浅草橋西口やきとん」と出会った瞬間でした。
当時、毎月いくら懐に入るか、そればかりを気にしていました。家に入れなければいけないミニマムのカネをつくるにも四苦八苦。だから、「浅草橋西口やきとん」の客になってからも、そうそう通えたわけではない。昔も今も、たいへん良心的な価格で飲兵衛を喜ばせる店ですが、それでも、30歳の駆けだしライターは通えなかった。
店がガード下から現在の場所に移った頃から少しずつ行く頻度が増えて、『酒とつまみ』というミニコミ雑誌を事務所の仲間と一緒に創刊した後は、一時、足繁く通った。店に雑誌を置かせてもらい、たくさん販売していただいた。
前置きが異常に長くなったけれど、この店は私にとって、たいへん大きな恩のある酒場なのである。

■うん、やっぱり、この味だ!
「タン塩。瓶ビール。あっ、ナンコツもね。これはタレで」
先日、久しぶりで店を訪ねたとき、23年前とほぼ同じ注文が口をついて出た。
焼き台にびっしり詰めた炭が赤い。隣で立って飲んでいるオヤジさんが頼んだカシラを乗せると、白い煙が立ち上った。
ナンコツの串から先に口へ運ぶ。熱々の軟骨を噛み砕く。コップの赤星をぐびりとやる。うまい。この味だな、と思う。
タン塩も口へ運ぶ。やはり、この味だなと思う。塩がきいていて、私好みなのだ。

焼き台を預かる彼は、相変わらずの細身だが、ちょっと風格が出た。私らが通い詰めたときはまだ、青年だった。
「何年になる?」
「14年ですよ。40超えました」
「そうかあ、オレも、53だよ。参るねえ」
開店直後からやってくる客の注文はひっきりなしに続く。それを澱みなく捌いていく姿は見ているだけで楽しい。

ホールを仕切るカズちゃんも声をかけてくれた。
「体調、大丈夫ですか」
「もうバリバリだよ。昔より飲んでる」
「そりゃよかったです」

そこへお店の大将が登場した。大将も言う。
「身体は大丈夫ですか」
「はい、おかげさまで、元気に飲んでます」
「そうですか、それはそれは」
ニコニコと笑ってくださる。肝臓の数値が悪くてひと月ほど酒をやめた時期が、何年か前にあった。そのときのことをみなさん覚えていてくださって、行くたびに気にしてくれる。人の出入りが多い賑やかな酒場であるのに、そういう細かい配慮が行き届く。

塩煮込みがうまい。煮込みは味噌仕立てが主流だけれど、私はこの店の塩煮込みがとにかく好きで、行けば必ずといっていいほど頼んできた。
■楽しく頑張る先輩たちが、元気にしてくれる
2台ある焼き台のひとつに、大将が立って、つくねを焼きはじめた。これこれ、このつくねがまた、うまいのだ。
つくねと厚揚げねぎま、それからウインナーなども追加する。同行の編集Hさんは豚足にも触手を動かした模様である。
撮影もあらかた済んだ時点で、写真のSさんも飲み始める。
「ああ、こんな店が家の近くにあったら、毎日通いますねえ」

まさにその通り。気持ちはよくわかる。昔、この店で閉店近くまで飲んでいたころ、近くに部屋があったらいいのになあ、と、実にたびたび思ったものだった。
鳥越神社の近くに安いアパートはないか。それが見つかれば、ここで飲み、いったん部屋へ引き返してから道具一式を持って銭湯へ出かけ、ゆっくりと四肢を伸ばして入浴する。帰りにはまた、コンビニで焼酎でも買って帰ろう。
所帯持ちがそういうことを考えては不届き千万なのであるけれど、そんな憧れを、この店が私にもたらしていたのは事実だ。
「西口やきとん」と、蕎麦屋と中華屋があればオレはまったく問題ないと本気で思っていたころの話である。

レモンハイボール(店ではボールと呼ぶ)を頼む。焼いたニンニクを味噌ダレにつけて口へ放り込み、2本目の赤星の残りをぐびっとやってから、ボールの小ジョッキにも口をつける。
懐かしい味がする。それくらい、たくさん飲んだ酒なのだ。なんだか、妙に嬉しくなってくる。店は盛況。お客さんは次々にやってきて、早い人は見事なくらいすきっと飲んで帰って行く。
80代というお姐さんもやってきて、焼き台の前に立った。ボールの小を頼む。小柄だけれど元気な姐さんで、店の人も、周りの客も、気にかける。声をかける。週に何度も来るという常連さんだからだ。
聞けば大将も古希を過ぎている。昭和20年生まれ、今年の年男だ。
「やれる仕事があるのはありがたいことですよ。みんなに助けてもらってやっているんです」
にこやかに、謙虚に、そんな言葉を口にする。

先輩たちが、楽しく頑張っている。そういう姿を見て、50代ちょいちょいで、くたびれたのなんの言ってはいかん、と改めて思う。
大将がこの店を開いたのは昭和48年。もう44年も前のことだ。一代で40年以上、もつ焼き屋を守るというのは、並大抵じゃない。ハンパねえのである。
それに比べて私のライター稼業など、まだ、23年。大将の経歴に照らし合わせれば、まだ折り返し地点なのだ。私はボールを飲み干し、また、赤星にもどってぐびりとやり、この数年ご無沙汰をしたこの店に、また通い直したいと思った。
行けば必ず元気にしてくれるこんな酒場、めったにあるもんじゃない。

取材・文:大竹 聡
撮影:須貝智行








 ブックマーク一覧
ブックマーク一覧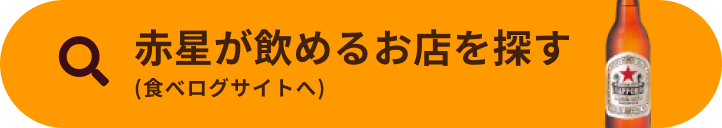





 と赤星
と赤星
 と赤星
と赤星
 と赤星
と赤星