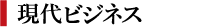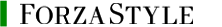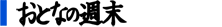※撮影時以外はマスクを着用の上、感染症対策を実施しております。
西浅草に、「大根や」という小さな飲み屋がある。ずっと来たいと思っていた店だ。
店の正面に立って眺めれば、店名が墨書された生成りの提灯は屋根付きで、縄のれんのかかった引き戸の脇にはいくつかの植木鉢と、この季節、蚊取り豚が鎮座して、その横に外箒が立てかけてある。

シブい。
恐る恐る店に入り、ビールを注文すると、女将さんは冷蔵庫からサッポロラガービール、赤星を取り出す。

普通、栓抜きを下からあてがい、柄の部分を引き上げて開栓するが、女将さんは栓抜きを栓の上からあてがった。ちょっと驚き、注目すると、栓抜きの穴の開いた部分から延びる柄が、絶妙に折り曲げてあるのだ。
女将さんはその曲がった栓抜きの刃を栓の縁に噛ませる。すると柄は見事に水平になった。噛み合わせた栓のところに左手を添え、右手を10センチほど浮かせると、てのひらを下に向け、水平になっている柄に振り下ろした。

シュポンッ!
小気味のいい破裂音がして栓は開いた。はい、いらっしゃい!とビールが言ったのかもしれない。
シビレる。

■出身は深川、チャキチャキの江戸っ子
店の開業は1967年。昭和で言うと42年。今年は2022年だから、55年目になる。
女将さんの名前は安藤幸子さん。取材に先立って昨年秋に刊行された『神林先生の浅草案内(未完)』(神林桂一著・プレジデント社刊)を読んで予習していたから、多少のことは頭に入っている。

開業時から使っているカウンターが松材ということも知っている。そこにコップを置き、ビールを丁寧に注ぐと、ついにやってきたな、という思いがする。一度行ってみてくださいよと、浅草生まれの友人に勧められていたからだ。
コップを持ち上げると自然に目線も上向いて、女将さんが背にする立派な棚が目に入る。聞けばこれも開店以来の棚で、材は秋田杉だという。

その端っこに、大ぶりのカツ箱(かつお節削り器)があり、女将さんはそれを取り出して、こんなの珍しくもないでしょ、と言いながらシャッシャッと掻き、はい、と言って筆者のてのひらにのせてくれた。いい香りが鼻をつき、口に含めばとろけるうまさだ。
店を開いたとき、女将さんはまだ20代。それ以前は都バスの車掌さんをしていた。労働組合に加入し、1960年の安保反対闘争のデモにも参加している。一方で、都バスの運転手さんや車掌さんたちと一緒に、運転手さんが勧めるもつ焼き屋の暖簾をくぐったりもした。カウンターにのっている総菜を見つくろってもらいながら、お話を聞く。

「都バスの車掌を辞める頃はね、もう都電もなくなってきていたし、バスもワンマン化が始まっていた。職場の仲間もみんな辞めるというし、都の他の職場の職員にはなれると組合の人から言われたけど、この際、辞めますと言って辞めちゃった。さてどうしようか、何も考えてなかった。
私は国際劇場が好きで通っていたんだけど、両親から、これからどうするんだって言われてね。食べ物屋でもやろうかと思うのって言ったら、お前に食べ物屋なんかできない!って。でもね、国際劇場の女の子たちが、なんかやんなさいよ、あたしたち溜まりに行くからって」

ちなみに女将さんは料理は得意ではなかったという。けれど、この西浅草で、小さな飲み屋を開いてしまうのだ。
そして開店初日。松竹(国際劇場は松竹の東京の本拠地)の衣装担当の男性が来てくれた。
「ご飯炊いてって言うから焚いて出したら『これじゃダメだ。全部捨てて焚きなおせ』って叱られた。それで丁寧に焚きなおして出したら、よし、じゃ、俺は帰るよって1万円札を置いていったの。浅草だなって思ったわ。がんばれって応援してくれたのね」

女将さんのご出身は深川でチャキチャキの江戸っ子ではあるが、娯楽と遊興の街としておそらくは日本一であった浅草の賑わいや、そこに生業をもつ人々の気風はひと味もふた味も違ったことだろう。
「店を始めたばかりの頃はズブの素人だから、お客さんが来ると恐くてね、カウンターの中でしゃがんじゃったりしてた。でも、店を閉めて帰るときにすぐそこの神社を通りかかると、客引きが3人いてね。今日はお客は何人来てくれた?って聞くの。
そうか来てくれたか、よかったな。俺たちみてえなのが行って変な噂が立つといけねえから俺たちは行かれねえけど、まあ、気を付けて帰れよって、声かけてくれた。複雑な気持ちだったけど、すごく励まされたわね」

■常連客は、エロ事師から日銀総裁まで
皿に盛られた総菜に箸をのばす。
ほうれん草のお浸しがうまい。茹で加減、醤油の加減、軽くふったカツブシ、その全体がとっても具合がいいのだ。えぐみもないし、苦みも強くないが、ほうれん草の味がしっかりする。

煮たそら豆も、イカも、見た目の色ほど塩辛いわけではなく、ホッとするうまさ。小さな飲み屋のカウンターで懐かしい家庭の味に出会う幸福を思い起こさせてくれる。
サツマイモの甘辛煮は言わずもがな。おいしい、懐かしい、それから、うれしいと言いたくなる。

「大根はハリハリ漬けですか?」
「そう、ああ、うれしいわ。パッと見てハリハリ漬けって言った人、最近そうそういないから!」
なんのことはない。筆者の好物なのである。女将さんのハリハリ漬けは昆布の出汁と酢の塩梅が絶妙なのだろうか。上品で、さっぱりしていて、ビールはもとより、日本酒でもウイスキーでも何にでも合うだろう。

冒頭で著作について触れた都立浅草高校教諭の神崎桂一氏をはじめ、この店は多くの人に愛されてきた。野坂昭如氏の小説『エロ事師たち』のモデルであり、元祖風俗ライターとも呼ばれた作家、吉村平吉氏も常連の一人だった。
「いつもカウンターの端っこに座ってね、ビールを飲んでるの。やさしい人でしたね。荒い声なんか一度だってあげたことなかった。神林先生は飲んで食べて、よく笑って。私、神林先生の悪口を言う人を知らない」

第26代日本銀行総裁、三重野康氏もこの店の客のひとりだ。大胆な金融引き締めでバブル景気を鎮静化させ、平成の鬼平と言われた総裁である。
「なんか少し食べて、ビール1本、焼酎も1杯くらいで、はい、ごちそうさんって、帰るんです。副総裁のとき、うちに来ていて、アメリカにいる総裁からここへ電話が来たことがある。なんていうの、なんか決める会議。そうそう、公定歩合。その会議の前日だったのかな。
あのときは、驚いたわ。三重野さんは、私を可愛がってくれました。読んで勉強しなさいってご著作をくださったりね。私は読んでもわからいんだけど(笑)。人間的にとても立派な方でしたね」

庶民の営みに心を寄せる人たちに愛される店、それが「大根や」だ。開業当初から、厳しい芸能の世界に生きるSKD(松竹歌劇団)の女性たちがここへ通ったという事実も、それを裏付けているだろう。
「SKDの女の子たちを目当てに来る男の人を、ダメよ帰ってって、入れないんだから、私は生意気だった。筋金入りの生意気(笑)。でも、生意気でしたけど、数えきれないくらいの人と知り合って親しくさせていただいた。浅草では、人の上下がないからね」

■ムロアジのくさやで一杯やりながら
いつまででも聞いていたい話を聞く間にも、くさやと熱燗を注文していて、それが、カウンターに出てきた。身をほぐしたくさやが、抜群にうまい。
たいへん妙な言い方になるが、臭くない。品がある。これ、実にうまいと思う。

「お酒と醤油と、それから七色をね」
あっ、酒をふるのか……。それと、七味唐辛子か……。
うまさの秘密ここにあり、とか早合点をするわけだが、あまり大きくはないムロアジのくさやの質がいいのが第一か、とも思う。

くさやを口に運び、燗酒を啜る。撮影の段取りをあらかた終えた編集Hさんが隣でらっきょうを齧りながら赤星をぐいっとやるのを見て、私は自分のコップにも、彼が頼んだ冷たいビールを注ぐ。そして、くさやと合わせて、にんまりする。申し分ないのである。
ビールはなぜ、赤星なのか。ふと思い立って聞いてみた。

「最初の頃、サッポロビールの営業の人が、ほとんど毎日来てくれたの。おもしろいおじさんでね。毎度毎度、がんばってねって言う。それから、僕らもがんばらせてねって。ひっきりなしに来てくれるんじゃ、あたしもね。よくわからなかったんだけど、サッポロを取るようにしたんです。
あるときお客さんからビールはサッポロの赤だぞって言われて。それを酒屋さんに言ったら、粋なことを言うお客だねって。それからうちはずっとサッポロの赤。誰か新規で店を出す人がいると、あたし言うの。あんたサッポロの赤、取んなさい。そうすっとあか抜けてると思われるからって(笑)」

いい話だなあと太く息をついて、コップの赤星を飲み干し、徳利も空にして、もう1本お願いしますと言いながら、女将さんの背後の棚に貼り付けてある品書きのひとつに目がとまる。入店直後から気になっていた短冊の1枚。
あぶしらさ? 否、あぢしらき。はて???
Ajishiraki……? 無理やりローマ字に変換したその瞬間、わかった!

「ぢ」は「じ」だ。昔はラジオをラヂオと書いていた。その名残りかと推測できる。「しらき」の方は、女将さんが朝日新聞をアサシシンブンと発音しがちなバリバリの江戸っ子であることに鑑みて、「ひらき」であると推測できた。
つまり、あじひらき。鯵の開きだ。

ムロアジのくさやで一杯やっている最中ではあるのだけれど「あぢしらき」も頼もう。Hさんと私は意見の一致を見た。
そして、この一枚の開きが焼き上がるまでの間、我々はまた赤星を飲み、燗酒をやる。なんと楽しい夕暮れ時であることか。

(※2021年5月27日取材)
取材・文:大竹 聡
撮影:須貝智行








 ブックマーク一覧
ブックマーク一覧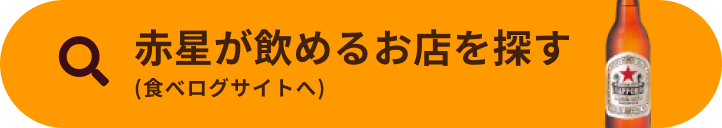





 と赤星
と赤星

 と赤星
と赤星
 と赤星
と赤星